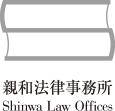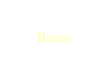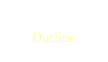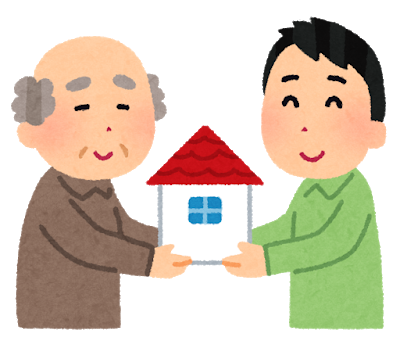相続で揉めるパターン2 不動産編の2
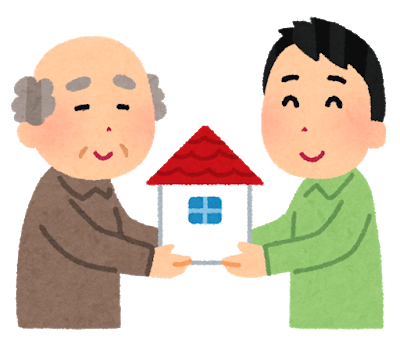
不動産は、一つとして同じものはありませんから評価が難しいものです。
一物五価とも言われる価格の違いがあります。
相続人間の遺産分割では、実勢価格(時価)がベースになります。
前回、マンションですら相続の話し合いでは評価が一致しないことをお話しました。最終的に、裁判所が選んだ鑑定士による鑑定評価で決着を見ることになりました。
相続人間の話し合い(遺産分割)では、不動産の評価は時価となります。
ところで、不動産の価格については、時価(実勢価格)以外にも、以下のような公的評価が公表されています。このため、不動産について、一物五価と呼ばれることがあります。
「公示地価」は、一般の土地取引の指標や公共事業用地を取得する際などに基準となる価格です。毎年3月下旬に国土交通省から公表されます。
具体的には、その年の1月1日における全国の標準地(2020年は計2万6000地点、うち7地点は調査休止)の1㎡当りの価格で、建物がある場合は建物がない更地として評価されます。
「基準地価」は、毎年7月1日における全国の基準値2万2000地点の価格で、9月下旬に都道府県の調査を基に公表されます。基準地は都市計画区域外や林地も対象(一部標準地と重なる地点もある)なので、「公示地価」の補完的役割も果たしています。
「固定資産税評価額」は、毎年の1月1日を基準として土地の所有者に課される固定資産税や都市計画税のほか、不動産取得税や登録免許税の算定基準となる価格です。各市町村(東京23区内は東京都)によって決定されます。「公示地価」の70%程度と言われています。
「路線価」は、土地の相続税や贈与税の算定基準となる価格で、毎年1月1日における価格が、7月初旬に国税庁から公表されます。評価額は、相続税路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当りの価格)を土地の形状に応じた補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて算出します。「公示地価」の80%程度と言われています。
以上のように、目的に応じて様々な評価方法があるのも不動産の特徴ですが、相続人間では、話し合い又は鑑定により時価を定めて分割することとなります。その際、上記の公表されている価格はあくまでも参考ということになります。
相続人本人は、不動産の価格についての考え方を十分理解されていないことも多いので、実際に住んでいる人が固定資産税評価額(一番低い評価になる)を主張したり、相続税を計算する過程で路線価(時価より低い)をなぜ用いないのかと述べることもあるので、最初によく説明を行って頂く必要があります。
続く