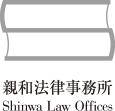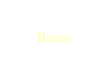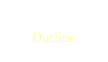社員のヘイトスピーチに対応する
弁護士の落合洋司氏が差別的発言のSNSで炎上しています。
社員のSNSでの発言について気を付けることも必要になります。
普段からの意識づけや、就業規則の整備を進めましょう。
弁護士の落合洋司氏がTwitterでの不適切な発言により、ネット上で炎上し、謝罪に追い込まれています。
落合氏は、今夏の参議院議員選挙にも立候補する予定でしたが、立憲民主党からの公認も取り消され、選挙への立候補も難しくなっています。Twitterでの一言が与えた影響は大変大きかったようです。
皆さんの会社でも、従業員がSNSなどで発信を行うことも多くなっていると思います。落合氏のように公的な立場ではない、あるいは匿名で行っているからばれないということで、気楽に発言している従業員もいるのではないでしょうか。
しかし、インターネット社会の恐ろしいところは、表現活動がすぐに拡散し、匿名であっても、実名や所属が暴かれてしまうことが多いことです。ですから、いつの間にか、発言者が所属する皆さんの会社までもが、同じように問題視されることが有り得るということを意識する必要があるでしょう。
では、SNSを禁止してしまうことはどうでしょうか。
簡単なようで、以下点から問題があると考えます。
まず、禁止したとしても、こっそりSNSを行う従業員は必ずいるでしょう。匿名でも活動可能ですから、だれがどんな活動をしているかはなかなかわかりません。禁止されていることをこっそりやることは、人に興奮を与えるので、表現も過激になりがちです。
次に、表現の自由を尊重することが求められます。
自由で民主的な社会をつくるためには、全ての人に自分の考えを明らかにする機会が与えられなくてはなりません。戦前の日本や現代でも独裁国家では、国の考えに反対する表現が禁止されていることからも明らかでしょう。
問題は、表現の内容に規制を設けることが、内容に問題のない表現までいつの間にか萎縮させたり、規制の対象に加わったりすることです。SNSを規制することになると、社員の活動の私的な領域を規制することになることも問題です。
誰だって、仕事以外のプライベートは規制されたくないですよね。
このように、就業規則での一律的禁止には問題が多いのですが、それでも犯罪などで会社の社会的評価にまで影響を与えたりする場合に懲罰の対象になるように、名誉棄損で損害賠償請求の対象になるような表現活動については就業規則で禁止しておく必要があるでしょう。
難しいのは、規則の定め方と、その具体的当てはめですので、弁護士等の専門家に相談してもらえるとよいと考えます。
そして、そもそも日頃から従業員に対して、ヘイトスピーチなどの差別的発言がなぜよくないのか、SNS出の発言の再注意すべきことは何かなどを教育していくことが大切ではないでしょうか。