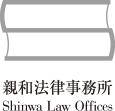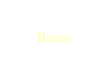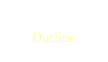目指せ!有給取得率100%!
今年も、多くの百貨店や商業施設は、元旦や二日から営業を始めました。
かきいれ時に働いてもらうことは企業にとって大事ですが、後々のトラブルを防ぐためにも、従業員にきちんと有給を取ってもらうよう工夫をしましょう。
毎年、有給が未消化で消えていき、従業員の不満が募っている
または、退職時に一気に有給を消化されてしまい、会社の業務に支障が出る…との問題が起きていませんか。
平成27年4月に国会に提出された労働基準法等の一部を改正する法律案(継続審議中)には、
「従業員に付与される年次有給休暇日数(10日以上)のうち5日は、毎年使用者が時季を指定して与えなければならない」
との内容が含まれています。
法律で取得を義務付ける必要があるほど、有給の取得ができていない現状があるようです。
一方、就業規則などで定めた以上になんとなく会社が休日に指定している日はありませんか?
実は、労働者の過半数を代表する者等との書面による協定がある場合、会社が、有給日数のうち5日を超える日数の取得時季を指定することができます(就業規則の定めも必要)。
つまり、有給が12日ある労働者について、5日については労働者の好きにとらせなければいけませんが、残りの7日については会社が時季を指定することができるのです。
たとえば、所定休日が土日祝とされている場合
今年なら、1月2日(火)、3日(水)、4日(木)、8月13日(月)、14日(火)、15日(水)、12月31日(月)を
有給取得日と指定すれば、7日分の有給を消化してもらうことができるのです。
現状ですでに会社指定の休日としている日を有給取得日とすることは難しいですが、たとえば、1月5日や、5月1、2日など、休みと休みの合間を特別に休みにすることを決めた場合などには、この日を一斉有給取得日として、有給消化をしてもらうことができます。
また、閑散期に有給指定日を定めておくことも考えられます。
計画的に有給を取得してもらうことが、会社にとっても良いことですので、これを機に、ぜひ、一度お考えください!