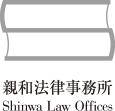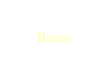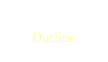遺言書の有無はどうやって調べる?
家族が亡くなったとき、遺言書をのこしているかどうかを知ることができる方法はあるでしょうか。逆に、自分が遺言書を作成したら、家族がきちんとその存在を知ってくれるでしょうか。
遺言書をせっかく作成しても、その存在を知られなければ、遺志を実現することはできません。近しい人に、どこに遺言書を保管しているか伝えることができればよいですが、伝えることで、書き直しを求められるなどかえってトラブルになることが心配、という方もいらっしゃいます。また、相続人の側としても、事情があって家族と疎遠になっているというケースもあるでしょう。
遺言書には一般的に公証役場で作成する公正証書遺言と、自分で作成する自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証役場で相当長期(遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年)保管されています。また、平成元年以降に作成されたものはシステムに登録されており、全国どこの公証役場でも検索することができます。検索したい場合は、遺言者が死亡したこと及び自己が相続人であることを証明する必要があります。なお、検索できるのは、いつ、どの公証役場で公正証書遺言をしたか、という情報だけですので、遺言書の内容そのものを確認するには、検索結果をもとに、該当の公証役場へ出向く必要があります。
次に、自筆証書遺言については、作成したら自分で保管しているというケースが多いでしょう。この場合は、信頼できる人に保管場所を伝えておかないと、発見されないまま遺産分割がなされてしまう可能性があります。避けるべきは、貸金庫に保管しておくことです。金融機関は、亡くなった人の貸金庫は相続手続をしないと開けてくれませんので、連絡のつかない相続人などがいると大変です。
このような事態を防ぐために、自筆証書遺言書保管制度があります。その名のとおり、遺言書を遺言書保管所(法務局)で保管してくれるという制度です。相続人は、全国の遺言書保管所で、遺言書が保管されているかどうかを確認することができ、保管されている場合には、遺言書の閲覧や、遺言書の画像情報を印刷した証明書を入手できます。
さらに、自筆証書遺言書保管制度の特色としては、通知という制度があります。
通知には、「関係遺言書保管通知」と「指定通知」の2種類があります。まず、「関係遺言書保管通知」は、相続人の誰かが遺言書を閲覧等したときに、他の相続人に対して遺言書が保管されていることを通知するというものです。次に、「指定通知」は、相続が発生したときに、あらかじめ遺言者が指定した人に対して遺言書が保管されていることを通知するというものです。現在のところ、「指定通知」で指定できるのは1名なので、配偶者を指定したもののその後離婚した場合や、養子を指定してその後離縁した場合など、相続人ではない人にしか通知がいかないという不都合が生じる可能性がありました(相続人ではないので、遺言書の閲覧等ができません)。
これが、10月2日より、3人を指定できるようになりますので、更に利便性がアップするといえそうです。
以上