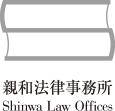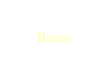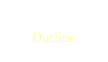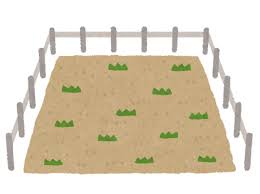相続登記の義務化
以前のメルマガ「遺産分割・登記はお早めに」(https://shinwalaw.jp/cms/mail-magazine/1520/)でもお伝えしたとおり、相続登記が義務化されます。相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されますので、あらためて確認しておきましょう。
近年、相続登記が長期間なされないことにより、いわゆる所有者不明土地が増えていることが問題となっていました。
この問題を解消するためのひとつの方策として、2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。すなわち、相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割協議がまとまった場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのに登記申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。
気をつけなければならないのは、2024年4月1日よりも前に発生した相続についても、義務の対象になるという点です。ただし、3年の起算点は、「知った日」と「施行日=2024年4月1日」の遅い方とされています。
ところで、遺産分割がなかなか成立しない場合や、相続人の調査が大変な場合には、相続登記の申請をすることが困難です。このような場合にも相続登記の申請義務を果たすための制度として、「相続人申告登記」が設けられました。この相続人申告登記は、
①登記簿上の所有者について相続が開始したこと
②自らがその相続人であることを申告すればよく、自分が相続人であることを明らかにする戸籍謄本等を準備すれば足ります。
この相続人申告登記の制度も、相続登記の義務化と同じく2024年4月1日からスタートします。
なお、正当な理由の例としては、
⑴相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り,戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
⑵遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
⑶申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
があげられています。
このような事情がない限り、早めに相続登記を済ませる、難しい場合は相続人申告登記を行うという対応が必要になります。
以上