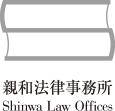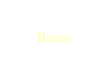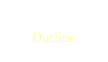民法改正により賃貸借が変わりました(続編)
本年4月1日に改正民法が施行されました。先月は皆様に身近な賃貸借継続中のルールについてお話しました。今月は、第二弾として、賃貸借終了時のルールについてです。
賃貸借終了時のルールに関する改正点は、①賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化、②敷金に関するルールの明確化です。いずれも裁判実務を明文化したものといえますが、重要な内容ですので、改めて振り返っていただければ幸いです。
①賃借物の原状回復義務及び収去義務等の明確化
賃貸借契約が終了した場合、賃借人は、賃借物を原状に戻して賃貸人に返還しなければならない義務を負っています。この原状回復義務の範囲について、旧民法では、一般に通常の使用収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化はその対象に含まれないと解されていたものの、明文の規定はありませんでした。
そこで、改正民法621条は、賃借人は賃借物を受け取った後に賃借物に生じた損傷については賃貸借終了時に原状に回復させる義務を負うことを原則とし、例外として、(ア)賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗及び賃借物の経年変化、及び(イ)賃借物の損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、原状回復義務を負わないと明記しました。
②敷金に関するルールの明確化
敷金とは、賃貸借に基づいて賃借人が負う賃料等の金銭債務を担保するため、賃借人が賃貸人に交付する金銭のことです。皆様にとってもなじみのある言葉だと思いますが、意外にも、旧民法では敷金についての明確な定めはありませんでした。
そこで、改正民法622条の2は、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義しました。注意していただきたいのは、この定義に該当するのであれば、契約書において「保証金」と記載していたとしても敷金に該当するということです。
また、同条は、判例に従い、敷金返還債務の発生時期を賃貸借が終了し賃借物が返還された時等とし、その額は受領した敷金額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額であることなどを定めました。
他の改正点についても、来月以降にお話させていただこうと思います。