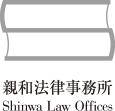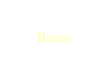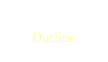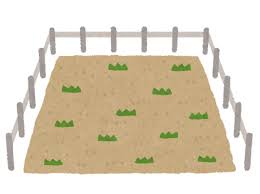遺言作成時、配偶者居住権の存続期間をどう書くべきか。
相続法が改正され、2020年4月1日以後作成する遺言から配偶者居住権を定めることができるようになります。
ただし、配偶者居住権の定め方を誤ると、配偶者を守るどころか、配偶者の負担を増やしてしまうことになるので、注意が必要です。
相続法改正により新たに、「相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、相続開始後、終身その建物を無償で使用することができる権利」(配偶者居住権)が制定されました。
当該配偶者居住権も遺産分割協議等の際に相続財産として評価されますが、その算定に際しては、相続開始時点における配偶者の平均余命等が考慮されるため、実際に相続が開始してみないと、配偶者居住権の評価額が判明しないということになります。
そのため、相続開始時に配偶者の年齢が若い場合などの場合には、配偶者居住権の評価額が高くなり、他の相続人の遺留分を侵害したとして、金銭を支払うことになったり、また、想定外の相続税を納税することにもなりかねません。
一方、遺言書を作成する時点では、自分がいつ死ぬか(死んだ時点で配偶者は何歳か)がわかりませんので、固定期間とする定めをおくこともリスクがあります。
例えば、夫婦が40歳の時に、自身が80歳ころに亡くなると思って、夫が配偶者居住権の存続期間を10年とする(妻が90歳まであればよいという判断)遺言を作成したが、不幸にも50歳で亡くなってしまった場合、妻は60歳で出ていかなくてはならなくなります。
現時点で、どのように配偶者居住権を定めておけばこれらの問題が解決されるのか、議論は深まっていませんが、例えば、「配偶者が定める期間」と遺言に定めることや、存続期間の定めを書かずに終身とし、相続開始時に配偶者に一部存続期間を放棄してもらう方法なども提案されています。
この件に関して、新たな動きなどがあれば、お伝えさせていただきます。