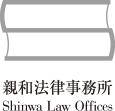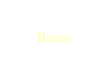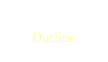節税のための養子縁組は無効?
相続税の額を減らすことを目的として、養子縁組を行うことは、よくあるケースかと思います。
その養子縁組、大丈夫でしょうか・・・?
相続税を計算する際、基礎控除の金額が法定相続人の数によって異なります。
相続税の額を減少させることを目的として、たとえば娘婿や孫などを養子とすることは、昔からよく行われてきました。
これが行き過ぎということで、基礎控除の計算の際に考慮できる養子の人数に、制限がかけられるようになったことは、皆様もご存じかと思います。
しかし、そもそも養子縁組という制度は、法律的な親子関係を新たにつくるためのものであって、相続税の額を減少させるためのものではありません。
だから、このようないわゆる「節税養子」は無効ではないか、という議論があります。
このような「節税養子」として、養子縁組は無効だと争われた事件で、最高裁判決が本年1月31日に判断を下しました。
この判決は、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう
「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」
としています。
胸をなで下ろしている関係者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただし、この最高裁判決も、「節税養子」の全てが有効であると判断したわけではないことに注意が必要です。
過去の最高裁判決は、「たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があったとしても、それが仮に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、養子縁組は効力を生じない」
としており、このような場合にあたるようなときは、やはり養子縁組は無効となります。
また、相続税法上、養子を相続人に含めることが「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」には、その養子の数を相続人の数に含めないこととされており(同法第63条)、養子縁組が有効であっても、相続税額の減少という効果を得られない可能性もあります。
相続税法の改正により、節税策としてよく紹介される「養子縁組」にも注目が高まっていると思われますので、今回ご紹介しました。