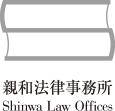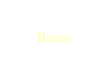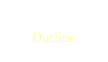株主が亡くなったら,誰が権利行使できる?
(概要)
株主が亡くなり、複数の相続人がいる場合、すぐに遺産分割協議が成立して次の株主が決まればよいですが、必ずしもそうとは限りません。株主が亡くなったからといって、会社の動きを止めるわけにはいきません。その間、誰がどのように株主としての権利を行使できるのでしょうか。
(本文)
例として、次のようなケースを考えてみます。甲社の株式300株を保有する株主Xが亡くなり、3人の子ABCが共同相続人となりました。Xの介護をしてきたABと、長い間音信不通だったCとが対立し、遺産分割協議が成立しない段階で、甲社の取締役の改任時期が迫っています。
この場合、各相続人の相続分は3分の1ずつなので、100株分ずつの議決権をそれぞれ行使できる・・・のではありません。
ABCは300株の株式を3分の1ずつの割合で準共有します。そして,300株分の議決権をどのように行使するかは,会社法が次のような定めをおいています(106条)。
「株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りではない。」
では、「当該株式についての権利を行使する者1人」はどのように「定め」るのでしょうか。この点については、「当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り」持分の過半数で決めることができます。
先ほどのケースであれば、ABの持分をあわせると3分の2で過半数を占めますから、彼らの意見が通ることになり、例えばAが300株分の議決権を行使できることになります。よかった・・・
では、次のようなケースであったらどうでしょうか。甲社の全株式300株を保有するオーナー兼会長であったXが亡くなり、3人の子ABCが共同相続人となりました。Xとともに甲社を経営してきた現社長のAと、それぞれ気ままに暮らしてきたB・Cとが対立し、遺産分割協議が成立しない段階で、甲社の取締役の改任時期が迫っています。
こちらの場合も、理屈は同じですので、B・Cが結託して、A社長を引きずり下ろし、自分たちが経営者になることができてしまいますね。
こんな恐ろしいことにならないために、贈与や遺言書の作成など、生前に準備を進めておくことが必要です。