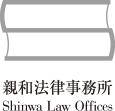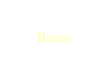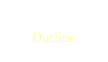暗証番号、パスワードの重要性
暗証番号、パスワードが盗まれると、財産も盗まれます。
厳重な管理と、定期的変更が大切です。
第三者が推測できない番号にしてください。
ATMに並んでお金をおろそうと列に並んでいると、前に高齢のおじいさんが、紙をもって一所懸命振込をしようとしています。
しかし、なかなか振込ができず行員の人がやってきて話を聞き、別室に連れていかれました。振り込め詐欺にあったのでしょうか。最近は、高齢者の自宅に、警察官を装って訪れ、キャッシュカードの暗証番号を聞き出してキャッシュカードを預かったふりをして、預金を下ろすという手口も増えているようです。
高齢者だと騙されるリスクがあるのですが、皆さんの会社のインターネットバンキングなどでは、ネットを通じてハッキングされてパスワードが盗まれてしまうなどと言うこともよくあるようです。
暗証番号やパスワードが盗まれて預金が下ろされてしまった場合、その責任は誰にあることになるのでしょうか。
キャッシュカードの場合、偽造カード法という法律があり、故意または重大な過失で払い戻しが行われた場合は、預金者の自己責任になります。
重大な過失とは、例えば、預金者が他人に暗証番号を伝えた場合、暗証番号をキャッシュカードに書き込んでいる場合、自らキャッシュカードを安易に他人に渡した場合などが考えられます。
キャッシュカードの場合は、振り込め詐欺などにひっかかった高齢者の被害が中心になります。
インターネットバンキングのハッキングによる被害も増えています。報告があっただけでも、多い年度では年間2000件近く、25億円以上の被害額が発生しています。発生件数や被害額を聞くと、他人事とは思えずドキッとした方もいるのではないでしょうか。
インターネットバンキングでの被害を防ぐためには、
➀セキュリティ対策ソフトを導入し、こまめにアップデートするよう心がける。
⓶基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に保つ。
⓷身に覚えがないメールに添付されたファイルは開かない。不審と思われるウェブサイトの閲覧は避ける。
不必要なプログラムや、信 頼の置けないウェブサイトからプログラムをダウンロードしない。
などの対策や、銀行推奨のセキュリティ対策を実行しておくことが望ましいです。
毎日のようにネットと接続していると、銀行に成りすましてメールが来たりするので、
⓷については特に注意が必要です。
ネットのセキュリティについては、慎重すぎるくらい慎重に対応しましょう。
以上