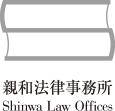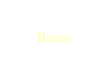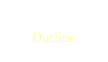会社の営業秘密、どのように守っていますか?
営業秘密の侵害事犯の検挙数が過去最多となっています。
回転寿司チェーン店といえば・・・で、パッと数社が思い浮かびます。その一つでもある「かっぱ寿司」を運営する会社の元社長が、競合する「はま寿司」の営業秘密を持ち出したとして元社長と運営会社が不正競争防止法違反で訴追されたことは、皆さんの記憶にも残っているところかと思います。その後の刑事裁判では、元社長が「はま寿司」の仕入れや原価に関するデータを持ちだしたことを認めています。
情報が一番の価値といっても過言ではない現代社会において、いかにして価値のある情報を入手するか、そして管理するか、は大変重要なパートとなります。
ビジネスのちょっとした場面で、「これは営業秘密ですから。」なんて言葉を使うことも少なくはないと思います。契約等により守秘義務を定めることはよくあるかと思いますが、「営業秘密」として刑事責任を追及したり、情報を取得した第三者に対して差止請求する等の法的保護を受けるためには、意外とハードルが高いことを知っておく必要があります。
不正競争防止法により保護される「営業秘密」に該当するためには、
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
③公然と知られていないこと(非公知性)
の3要件の全てをみたす必要があります。
そして実務において一番難しいのが①秘密管理性です。
単に、秘密だからね、と言っているようなレベルでは全く意味がありません。「かっぱ寿司」の刑事裁判でも、持ち出されたデータが「営業秘密」に該当するかが真っ向から争われているようです。
秘密管理性が認められるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が、具体的状況に応じた経済合理的な秘密管理措置によって、従業員に明確に示され、結果として、従業員が当該秘密管理意思を容易に認識できる(換言すれば、認識可能性が確保される)必要があります(経済産業省ガイドライン)。
例えば、紙媒体であれば、ファイルの利用等により一般情報からの合理的な区分を行ったうえで、基本的には、当該文書に「マル秘」など秘密であることを表示する、又は施錠したキャビネットに保管する。電子媒体であれば、営業秘密たる電子ファイルを開いた場合に端末画面上にマル秘である旨が表示されるように、当該電子ファイルの電子データ上にマル秘を付記(ドキュメントファイルのヘッダーにマル秘を付記等)、営業秘密たる電子ファイルそのもの又は当該電子ファイルを含むフォルダの閲覧に要するパスワードの設定等です。
顧客情報や権利化しない技術情報等、会社の生命線ともいえる情報については、是非とも、秘密管理措置を講じていただきたいと思います。
以上